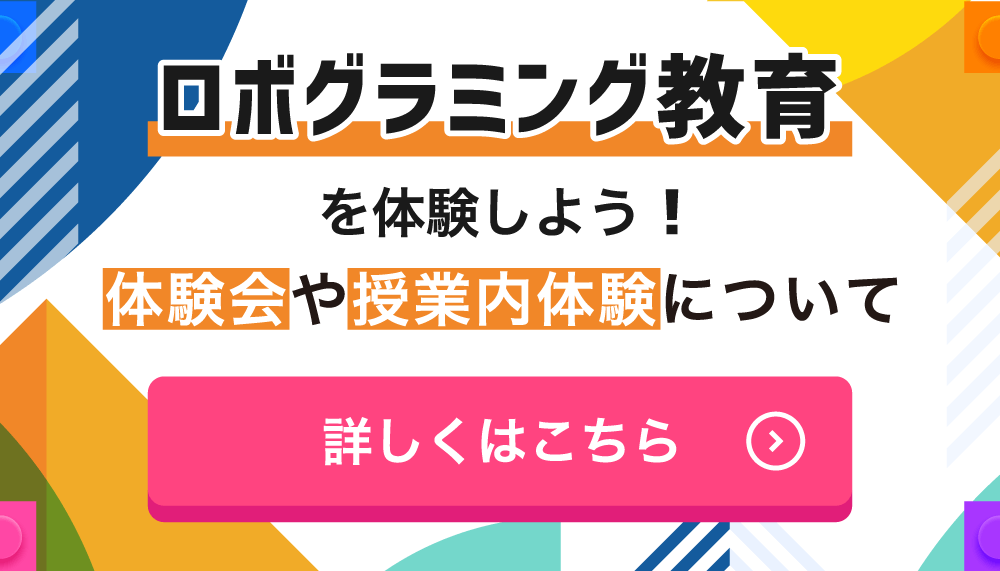2022.06.21
STEAM教育とは?今さら聞けない!詳しい解説。
STEAM教育の読み方や語源
まずはそもそも「STEAM教育」っていったいなんて読むの?
そう思った方も少なくないのではないでしょうか。
ステアム?ステーム?
正解は「スティーム教育」と読みます。
また、STEAM教育とは下記の5つの言葉の頭文字をとって作られています。
①科学=Science
②技術=Technology
③工学(ものづくり)=Engineering
④芸術=Art
⑤数学=Mathematics

5つの言葉の頭文字をとると「STEAM」という言葉になります。
※元々は「STEAM」の“A”がない「STEM(ステム)教育」という言葉が先に広まりました。
その後、Artという言葉が付け加えられてSTEAM教育へと発展しました。
STEAM教育とは
STEAM教育とは、上記で上げた5つの分野や領域を重視する教育方針のことを言います。
発祥は日本ではなくアメリカです。
アメリカが科学分野でのさらなる発展を高めるために国全体で推進をしている教育方針です。
その後、日本にもSTEM教育やSTEAM教育という言葉が入ってきて広まりました。
STEAM教育の狙い
STEAM教育の狙いは、次世代を生きる子供たち、AI時代を生きる子供たちが、将来きっと必要になるであろう能力を養うことです。
例えば、
・文章や情報を正確に解釈する力
・科学的、論理的に考える力
・感性や好奇心、探求心
などです。
STEAM教育がなぜ注目されるのか
STEAM教育がここまで注目される大きな原因の1つが「テクノロジーの飛躍的な進化」があげられます。
具体的に例をあげると、スマホやタブレットなどのデバイスの進化、モノとネットがつながるIoT、そして1番大きいと言われているのがAIの進化や活用です。
こうしたテクノロジーの進化は今後も加速し続けます。
そうなると何が起こるのか?
今と20年後では、社会に必要とされる人材が全く変わってしまうんです。
テレビやニュースでもよく耳にするかと思いますが、「20年後には今ある仕事の半分はAIにとって代わられる」と言われています。
大げさな話ではなくて実際に私たちの日常にもそうした予兆はたくさんあります。
新聞でニュースを読むのが当たり前だった数十年前、でも今はスマホでニュースを読むのが当たり前です。
年賀状や手紙も、メールへと代替えされ、さらにはもっと手軽なチャットへと移り変わりました。
こうした例と同様に、今当たり前に使っている物や道具、そして当たり前に存在している仕事も、20年後にはなくなっている可能性が高いです。
つまり、STEAM教育は子どもたちの未来のための教育なんです。
STEAM教育推進の壁
しかし、STEAM教育を日本で広めていくには1つ大きな壁があるといわれています。
最大の理由が、「教える人がいない」ということです。
小学校や中学校でも、国語や算数、理科の先生はいても、STEAM教育に精通した教員はいません。
まして、テクノロジーやプログラミングの分野までカバーできる教員を手配するとなると簡単なことではありません。
STEAM教育の今後
大きな可能性と同時に乗り越えるべき課題もあるSTEAM教育。
ですが、これからの時代の主人公である子どもたちには必要な能力です。
実際、わたしたちロボグラムのカリキュラムにも、科学、技術、ものづくり、芸術、数学、STEAM教育の5つの要素は非常に多く取り入れています。
わたしたちも、ロボット作りやプログラミング学習を通して、日本でのSTEAM教育のさらなる浸透によりいっそう貢献していきたいと思っています。
体験会なども開催しているのでお気軽にご参加ください
→ 体験会、授業参加